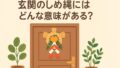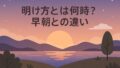新年の始まりを彩る行事のひとつ「十日えびす(十日戎)」は、関西を中心に多くの神社で開催され、商売繁盛や家内安全を願う人々でにぎわいます。
「十日えびすはいつから?」「参拝では何をするの?」と気になる方も多いのではないでしょうか。
本記事では、十日えびすの日程や起源、参拝の流れや縁起物の意味、さらには混雑を避けるコツまで詳しくご紹介します。
これから参拝を予定している方や、行事の魅力を知りたい方はぜひ参考にしてください。
十日えびすはいつから始まる?日程と由来
十日えびす(十日戎)は、毎年1月9日から11日までの3日間にわたり開催される伝統行事です。
関西を中心に多くの神社で行われ、特に兵庫県の「西宮神社」、大阪の「今宮戎神社」、京都の「京都ゑびす神社」が有名です。
商売繁盛や家内安全を願う人々でにぎわい、年始の風物詩として根強い人気を誇っています。
毎年の開催日(1月9日~11日)
十日えびすは、毎年決まって1月9日・10日・11日の3日間に開催されます。
- 9日(宵戎) … 前夜祭にあたり、十日戎の始まりを告げる日
- 10日(本戎) … 最も多くの参拝客が訪れるメインの日
- 11日(残り福) … 本戎に行けなかった人も参拝できる日
「残り福」という呼び方には、本戎を過ぎてもご利益が残っているという意味が込められています。特に商売を営む人々にとっては、一年の運気を占う大切な節目となっています。
各地で行われる十日戎(西宮・今宮・京都など)
十日戎は関西を中心に全国で行われますが、なかでも有名なのは以下の神社です。
- 西宮神社(兵庫):日本全国にある「えびす神社」の総本社。福男選びの行事でも知られる
- 今宮戎神社(大阪):大阪商人に親しまれてきた神社で、参拝客数は毎年100万人以上
- 京都ゑびす神社(京都):古くから京の町人文化と結びついた神社で、独特の参拝方法が特徴
地域ごとに雰囲気が異なり、各地の「十日えびす」をめぐるのも楽しみ方の一つです。
起源と「商売繁盛」の由来
十日戎の歴史は古く、起源は平安時代ともいわれています。
えびす様(蛭子大神)は七福神のひとりで、唯一日本由来の神様とされ、漁業や農業の神として信仰されてきました。やがて時代が進むにつれて「商売繁盛の神様」としても祀られるようになり、商人のまち・関西で盛んに信仰が広まりました。
今日では、商売を営む人はもちろん、家庭の幸せや学業成就を願う人々も多く訪れます。えびす様のにこやかな笑顔は、人々の一年を明るく導く象徴として親しまれています。
十日戎では何をする?参拝の流れと楽しみ方
十日戎では「商売繁盛で笹持ってこい!」という掛け声の通り、福笹や熊手などの縁起物を授かりながら、えびす様に一年の繁栄を祈願するのが中心となります。
参拝だけでなく、境内の屋台や行事も盛りだくさんで、大人から子どもまで楽しめるのが特徴です。ここでは、具体的な参拝の流れや楽しみ方を紹介します。
参拝の作法とお参りのポイント
十日戎での参拝方法は、基本的には一般的な神社参拝と同じです。
鳥居をくぐる前に一礼し、手水舎で手や口を清めたら、拝殿の前で「二礼二拍手一礼」の作法でお参りします。
特に有名なのは、大阪の今宮戎神社での「本殿横の壁を叩く」風習です。
えびす様は耳が遠いといわれるため、願いごとを聞き届けてもらうように壁を軽くたたく参拝者も多く見られます。こうした地域ごとのユニークな作法を体験できるのも、十日戎ならではの楽しみです。
福笹・熊手・縁起物の意味
十日戎の大きな魅力は「福笹」と呼ばれる笹を授かることです。笹は「繁殖力が強く、まっすぐ伸びる」ことから、商売繁盛や家運隆盛の象徴とされています。
福笹には、巾着や小判、米俵などの縁起物を自由に飾り付けていくことができます。
また、熊手も人気の縁起物です。「運や福をかき集める」という意味があり、関東では熊手が主流ですが、関西の十日戎では福笹が中心となっています。
縁起物を選ぶ時間そのものが、家族や仲間にとって新年の特別なひとときとなります。
屋台や催し物での過ごし方
十日戎は参拝だけでなく、屋台や催しも大きな楽しみです。境内やその周辺には、たこ焼き、たい焼き、ベビーカステラといった関西らしい屋台がずらりと並びます。子ども連れの家族も多く、初詣気分でにぎわいます。
また、西宮神社では「福男選び」、今宮戎神社では「宝恵駕行列(ほえかごぎょうれつ)」など、地域ごとに特色ある行事が開催されます。
単なる参拝にとどまらず、一大イベントとして楽しめるのが十日戎の魅力といえるでしょう。
商売繁盛を願う縁起物の選び方
十日戎といえば、福笹や熊手などの縁起物を授かるのが大きな楽しみです。
これらの縁起物にはそれぞれ意味があり、正しく理解して選ぶことで、ご利益をより身近に感じることができます。ここでは代表的な縁起物の特徴と選び方を見ていきましょう。
福笹に付ける縁起物の種類
福笹は十日戎のシンボル的存在で、笹の枝にさまざまな縁起物を飾り付けていきます。代表的な飾りには以下のようなものがあります。
- 米俵:五穀豊穣と商売の繁盛
- 小判や巾着:金運上昇や財運の象徴
- 鯛:「めでたい」にかけて、幸運を招く魚
- 打ち出の小槌:願いをかなえる力の象徴
神社の境内では福娘と呼ばれる巫女さんが福笹を授与してくれることが多く、明るい笑顔とともに福を授かるのも十日戎ならではの体験です。
熊手や大まぐろ奉納の意味
関西では福笹が主流ですが、熊手も縁起物として人気があります。
熊手は「福をかき集める」道具として、特に商人に重宝されています。サイズや飾りの華やかさはさまざまで、毎年少しずつ大きなものに買い替えることで「年々繁盛している」ことを表す習わしもあります。
また、西宮神社では「奉納まぐろ」も有名です。
参拝者が大きな生マグロにお金を貼り付けることで、金運や商売繁盛を祈願します。こうしたユニークな風習も、十日戎ならではの見どころといえるでしょう。
縁起物はどう持ち帰る?
縁起物を授かった後は、自宅や店舗の目立つ場所に飾るのが一般的です。玄関やレジ横など、人の出入りやお金の流れがある場所に置くと良いとされています。
また、翌年には神社へ返納し、新しい福笹や熊手を授かるのが習わしです。
古い縁起物をそのままにしておくのではなく、感謝の気持ちを込めて神社にお返しすることで、新しい一年のご利益がつながると考えられています。
十日えびすに行く前に知っておきたいこと
十日えびすは全国的にも人気の高い行事で、毎年数百万人もの参拝客が訪れます。
そのため、混雑やアクセス、参拝後の縁起物の扱いなど、事前に知っておくと安心できるポイントがあります。初めて参加する人も、事前準備をしておけばスムーズに楽しむことができます。
混雑状況とおすすめの時間帯
十日戎の中でも最も混雑するのは「本戎」にあたる1月10日です。特に夜は会社帰りの参拝者で大変込み合い、身動きが取れないほどになることもあります。
比較的ゆったりと参拝したい場合は、9日の宵戎の昼間や、11日の残り福の午前中が狙い目です。また、深夜や早朝は参拝客が少なく、静かにお参りできます。
小さなお子さん連れやご高齢の方にはこの時間帯が安心です。
アクセス・交通規制の注意点
大きな神社では、十日戎の期間中に交通規制が行われます。たとえば大阪の今宮戎神社周辺では車両の進入が制限されるため、公共交通機関の利用が推奨されています。最寄り駅から徒歩数分の場所にある神社が多いので、電車でのアクセスが便利です。
また、西宮神社では開門神事「福男選び」の影響で早朝に人が殺到することがあります。イベントを見たい人は早めの到着が必要ですが、混雑を避けたい場合は時間をずらすのがおすすめです。
参拝後の福笹の返納方法
授かった福笹や熊手は、その年の役目を終えたら翌年の十日戎で返納するのが習わしです。境内には返納所が設けられているので、持参すれば丁寧にお焚き上げしてもらえます。
「前年のものを返さないと新しい福笹を受けられない」という決まりはありませんが、感謝の気持ちを込めて返納するのが望ましいとされています。毎年新しいものに交換することで、気持ちも新たに一年を迎えられるでしょう。
まとめ
十日えびす(十日戎)は、毎年1月9日から11日まで開催される新年の大切な行事で、商売繁盛や家内安全を祈願する人々でにぎわいます。特に関西では、西宮神社や今宮戎神社、京都ゑびす神社が有名で、それぞれ独自の風習や行事を楽しめます。
参拝の際は「二礼二拍手一礼」の作法を守り、えびす様に一年の繁栄を願うのが基本です。福笹や熊手といった縁起物を授かることで、新しい一年の運気を呼び込むとされています。屋台や地域ならではの催しも豊富で、家族や仲間と過ごす楽しい時間となるでしょう。
また、参拝の際には混雑や交通規制に注意し、可能であれば比較的空いている時間帯を狙うのがおすすめです。授かった縁起物は翌年に感謝を込めて返納し、新しい福をいただくのが習わしです。
十日えびすは単なる祭りではなく、一年の始まりを晴れやかな気持ちで迎えるための大切な行事です。ぜひ参拝を通じて、えびす様の笑顔とともに明るい一年をスタートさせてみてください。